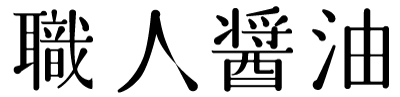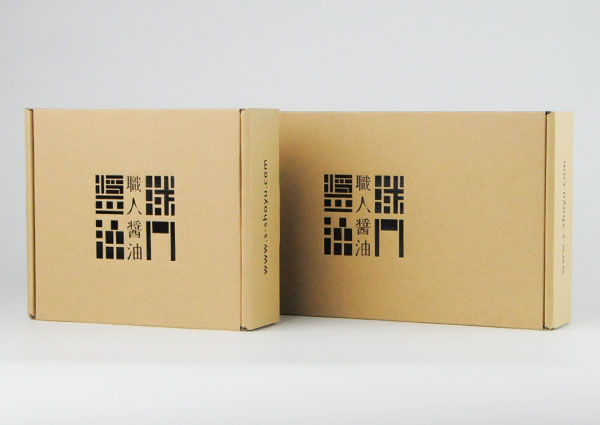豆腐を楽しむ醤油 5本
醤油を使い分けると冷奴がもっとおいしくなる!
職人醤油 No.

醤油の基本、知っていますか?
まずは、醤油の種類について簡単にご紹介。JAS(日本農林規格)では、醤油は5つに分類されています。白醤油、淡口醤油、濃口醤油、再仕込醤油、溜醤油の5種類です。(職人醤油では独自に甘口醤油を加え、6つに分類しています)これらの違いは、仕込みの期間や発酵の仕方、使う原材料などによるもの。だからこそ、それぞれに色・塩分・味わいが異なり、使い分ける楽しさがあるのです。
日本で生産される醤油のうち、約8割を占めるのが濃口醤油です。うま味・甘み・香りのバランスが絶妙で、どんな料理にも合う万能タイプです。白醤油と淡口醤油は、仕込み期間が短いため、色が淡く、味わいもあっさりしています。再仕込醤油と溜醤油は、仕込み期間が長く、原材料も多い。そのため、色が濃く、うま味も力強く仕上がります。

塩分控えめの淡口醤油の秘密は米麹
普通の絹豆腐にも、おいしい絹豆腐にも合う「淡紫」。
なめらかでとろける絹豆腐には、あっさりした淡口醤油がぴったり。
天然醸造の淡口醤油に、米麴をドボンと直接加えて仕込んでいます。この米麹のやさしい甘みが加わることで、塩分が一般的な濃口醤油よりも控えめになり、とてもまろやかな味わい。さらに香りも穏やかなので、素材の味を邪魔せず、そっと引き立ててくれるのが特徴です。絹豆腐の冷奴にかければ、醤油の味が出しゃばることなく、豆腐本来の甘みをふわっと引き立ててくれます。
実は、お客様から教えていただいたちょっと意外な使い方もあります。
「豆乳を飲みたいけれど、独特の香りや味わいが苦手で」という方が、試しに「淡紫」を少したらしてみたら、すごく飲みやすくなったんだそう。私は豆乳そのままでも大好きなんですが、「淡紫」を加えて飲んでみると、まるで“飲む豆腐”のような、やさしい味わいに。「淡紫」のやさしい香りが、豆乳をふんわり包み込んでくれる感じになるのです。豆乳が苦手な方にも、ぜひ試していただきたいアレンジです。

深いうま味と香りの余韻がたまらない
大豆のうま味や食感がしっかり感じられる木綿豆腐には「鶴醤」。
コクのある再仕込醤油が、豆腐の味わいと食感を引き立てます。
通常の濃口醤油は、麹に塩水を加えて仕込みますが、再仕込醤油は、塩水の代わりに濃口醤油を加えて仕込みます。つまり、一度できた醤油で、もう一度仕込む。これにより、塩分は控えめなのに、ぐっと濃厚でうま味の強い醤油に仕上がります。
「鶴醤」は、2年仕込んだ醤油をさらに2年熟成しているので、深いうま味と香りの余韻がたまらない、唯一無二の存在感を放つ醤油です。大豆のうま味や食感がしっかり感じられる木綿豆腐の冷奴にかければ、豆腐のしっかりとした食感と「鶴醤」の強い香りとうま味が見事に調和されます。まさに、ワンランク上の味わいに。
そのまま「鶴醤」をかけてもおいしいですが、私の定番は、ごま油を少したらす食べ方。実はこれ、お客様に教えていただいたのです。「鶴醤」とごま油、それぞれの香りが引き立ちあって、味も香りも、そして食感までもが満たされる、冷奴に仕上がります。
あえて単に「木綿豆腐」と書かずに「大豆のうま味や食感がしっかり感じられる木綿豆腐」と表現したのには理由があります。一般的な木綿豆腐におすすめの醤油については、この後でご紹介するからです。

大豆のうま味100% 3年熟成の溜醤油
特売の豆腐にもおすすめの「宝山丸大豆たまり」。
絹でも木綿でも、あっさり豆腐をぐっと濃厚に変えてくれます。
溜醤油は、淡口醤油・濃口醤油・再仕込醤油と、原材料の比率が異なります。大豆の割合が多く、仕込み水が少なめ。さらに、熟成期間も長く、じっくり時間をかけてつくられます。色も濃く、どろっと濃厚で、うま味は醤油の中でもトップクラス。よく、「九州の甘くてとろっとした醤油=溜醤油」と思われることもありますが、実はそれは別もの。溜醤油の主な産地は中部地方で、塩分濃度は濃口醤油とほぼ同じ。決して甘い醤油ではありません。ただ、その濃厚なうま味を、味覚として「甘さ」と感じる方もいらっしゃいます。これは砂糖のような甘さとは違う、素材の奥にあるまろやかさのようなものかもしれません。
「宝山丸大豆たまり」は、愛知県産の丸大豆を100%使用したグルテンフリーの醤油。溜醤油の中では、香りがよく、重たすぎず、使いやすいタイプです。だからこそ、特売の豆腐でも、「宝山丸大豆たまり」のしっかりとしたうま味と香りが豆腐を包み込み、おいしさを格上げしてくれます。ただし、かけすぎには注意。濃厚だからこそ、ほんの少したらす程度で十分です。かけすぎると、しょっぱく感じてしまうことがあるので、少量を意識してくださいね。
普通の絹豆腐には「淡紫」も紹介しましたが、あっさり味が好きな方は「淡紫」を。しっかり醤油の味も楽しみたい方は「宝山丸大豆たまり」をお試しください。

醤油らしさがまったくない「おいしい塩水」
大豆のうま味や食感がしっかり感じられる木綿豆腐には「しろたまり」。やさしい塩気と香りが、豆腐の風味をじんわり引き立てます。
はじめて白醤油を見る方は、その透明感にきっと驚くはず。熟成期間はわずか2〜3ヶ月。あっさりとした味わいと、きれいな琥珀色で、素材の風味をしっかり活かしてくれます。一般的な「濃口醤油」は、大豆と小麦が1:1の割合です。対して、白醤油はほぼ小麦でできていて、大豆はほんの少しだけ使われています。醤油というと大豆のイメージが強いかもしれませんが、実は醤油の成分の中で、大豆は主に「うま味」を担当し、小麦は「甘み」と「香り」を生み出しています。濃口醤油は、この「うま味」と「甘み・香り」のバランスが絶妙にとれていますが、白醤油は大豆はほんの少し、ほぼ小麦からできているため、醤油らしい深い味わいあまり感じられず、小麦の甘みや香り、そして塩気がメインになっています。
白醤油の中でも、この「しろたまり」はちょっと特別で、大豆を一切使っていないのです。原材料は、小麦・塩・焼酎のみ。通常の白醤油は少しだけ大豆を使っているので、ほんのり醤油らしい味がしますが、「しろたまり」はその「醤油らしさ」がまったくない。蔵元さんいわく「おいしい塩水」と表現するほど、小麦のやさしい甘みと香りがふわっと広がる、不思議なうまさが魅力です。 また、一般的にはカビの発生を防ぐためにアルコールを添加しますが、代わりに焼酎を使用しているのも特徴です。
大豆のうま味や食感がしっかり感じられる木綿豆腐には、再仕込醤油をかけて、大豆感をさらにプラスし、醤油との一体感を楽しむのもすごくおいしいのですが、豆腐そのもののおいしさを引き立てたいときには、やっぱり「しろたまり」が一番おすすめ。逆に、スーパーなどで手に入る一般的な木綿豆腐にかけると、「しろたまり」の塩気が前に出すぎて、「ちょっとしょっぱい」と感じることも。豆腐と「しろたまり」がうまくなじまず、バラバラに主張してしまうこともあります。

薬味も個性も味わいたいときに
おいしい絹豆腐には「えそ魚醤」。
やさしく甘みを引き立て、生姜やねぎなど薬味ともよく合います。
これまで4本の醤油を紹介してきましたが、最後に紹介するのは「魚醤」です。魚醤とは、魚を塩漬けにして発酵させた調味料。塩分濃度は醤油より高めですが、単なる塩気ではなく、魚由来の深いうま味とコクが特徴です。中でも今回おすすめしたいのが、「えそ魚醤」。この魚醤、まったくくさくないんです。一般的な魚醤は香りが苦手…という方も少なくないはず。私もそのうちの一人です。しかし、「えそ魚醤」だけは別。香りは穏やかで、うま味はしっかり。まるでさっぱりとしただし醤油のような感覚で使えるのです。「えそ魚醤」は、創業190年のヤマサちくわと、愛知県の醤油の老舗イチビキとの共同開発によって生まれました。実はイチビキでも30年前にイワシの魚醤づくりに挑むものの、特有の臭いに悩まされた経験がありました。練り製品の原料として最高級品とされる「えそ」を、ヤマサちくわでさばいた時点で塩漬けにすることで、臭いをぐっと抑えることに成功。そこに醤油の麹と乳酸菌・酵母菌も加えて発酵させることで、くさくないうま味たっぷりの魚醤が完成したのです。
だし醤油のような甘みはありませんが、だからこそ、とにかくさっぱり食べたい冷奴にぴったり。醤油とはまたひと味違う、豆腐のおいしさの楽しみ方、ぜひ試してみてください。

文:もーり(職人醤油)
オプションを選択