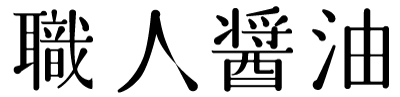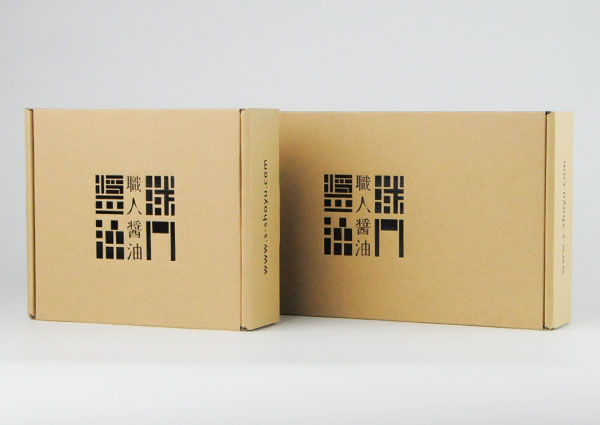まずはこれから始めよう!刺身入門編
職人醤油 No.

醤油の基本、知っていますか?
醤油は6つに分類されています。白醤油、淡口醤油、甘口醤油、濃口醤油、再仕込醤油、溜醤油です。これらの違いは、仕込みの期間や発酵の仕方、使う原材料などによるもの。だからこそ、それぞれに色・塩分・味わいが異なり、使い分ける楽しさがあるのです。
日本で生産される醤油のうち、約8割を占めるのが濃口醤油。うま味・甘み・香りのバランスが絶妙で、どんな料理にも合う万能タイプです。
◆白醤油・淡口醤油
仕込み期間が短いため、色が淡く、味わいもあっさり。
◆再仕込醤油・溜醤油
仕込み期間が長く、原材料も多い。色が濃く、うま味も力強い。
◆甘口醤油
ベースの醤油に甘味料をプラス。九州や北陸などの地域で根付いた味。
今回は、
【白身に合う醤油】淡口醤油、甘口醤油
【赤身に合う醤油】再仕込醤油・溜醤油
【迷ったときに頼れる1本】濃口醤油
をセレクトしました。

淡紫/末廣醤油(兵庫県)
【白身に合う醤油】の代表がこの淡口醤油の「淡紫」です。
淡口醤油(うすくちしょうゆ)は、その名の通り色が淡いのが特徴ですが、実は塩分は濃口醤油よりも少し高め。だからこそ、「薄口」という字はあえて使っていません。原材料は濃口醤油と同じく、大豆と小麦を1:1の割合で使用。醤油らしい味のバランスはきちんとありながら、熟成期間が短いため、色も味わいもあっさりしているのが特徴です。素材の色をきれいに見せたいときや、塩味をスッと効かせたい料理にはぴったり。たとえば、煮物やうどんつゆなど、食材のおいしさやだしのうま味を活かしたい料理におすすめです。
そんな淡口醤油の中でも、「淡紫」はちょっと特別な存在。天然醸造の淡口醤油に、米麹をドボンと直接加えて仕込んでいるのです。この米麹のやさしい甘みが加わることで、塩分が一般的な濃口醤油よりも控えめになり、とてもまろやかな味わいに仕上がっています。さらに、「淡紫」の蔵元・末廣醤油の特徴でもありますが、香りがとても穏やか。醤油味になりすぎず、やさしい香りで素材の味をそっと引き立ててくれます。
だからこそ、白身の刺身にぴったりなのです。タイ、ヒラメ、甘えび、ホタテ……そんな繊細な味わいの魚介には、「淡紫」を合わせてみてください。濃口醤油だと、どうしても醤油の味が前に出すぎてしまうことが多いですが、「淡紫」なら、やさしい香りとまろやかな味わいで、魚の甘みやうま味をふわっと引き立ててくれます。特に私、甘えびには衝撃を受けました。「甘えびって、本当に甘かったんだ……!」と。 「淡紫」がなかったら、もう白身の刺身は食べられない、と思うほどです。

マルクワ醤油 うまくち/桑田醤油(山口県)
【白身に合う醤油】の2本目は甘口醤油です。
甘口といっても、甘さはかなり控えめ。関東の方が使っても違和感がないほど、ほんのりとした甘みが特徴です。九州の甘口醤油の多くは、共同工場で生揚醤油までをつくり、その後、各社が火入れや味付けを行っているところが一般的ですが、この醤油をつくっている山口県の桑田醤油は違います。麹づくりから自社で手がけ、昔ながらの木桶で丁寧に仕込んでいます。また、この醤油の特徴は「混合醸造」という製法にあります。甘口醤油には、完成した生揚醤油にアミノ酸液などを加えて甘味やうま味を調整する「混合」もありますが、「マルクワ醤油 うまくち」は違います。諸味の段階でアミノ酸液を加え、一緒に熟成させていく「混合醸造」なのです。そのため、アミノ酸液特有の嫌な香りが発酵中にまろやかになり、甘口醤油にありがちなクセのある香りがありません。
木桶でじっくりと熟成された、ふわっと醤油らしい香りが感じられます。味わいも、濃すぎずすっきりとしたうま味に、ほんのりとした甘み。まろやかな口あたりで、白身の刺身をやさしく引き立ててくれます。「淡紫」と同じように、さっぱりとした醤油ですが、こちらはほんのり甘みがある分、まろやかな甘みで刺身を包み込むような味わいです。

濃紫/末廣醤油(兵庫県)
【赤身に合う醤油】の1本目は再仕込醤油です。
白身に合わせた「淡紫」と同じ、末廣醤油がつくっています。同じ蔵元の醤油でも、種類が違えば見た目の色も、味わいの濃さも、香りもここまで違うのかと驚かれるかもしれません。通常の濃口醤油は、麹に塩水を加えて仕込みますが、再仕込醤油は、塩水の代わりに濃口醤油を加えて仕込みます。つまり、一度できた醤油で、もう一度仕込む。そのため、塩分は控えめなのに、ぐっと濃厚でうま味の強い醤油に仕上がります。さらに「濃紫」は、自家製の米麹をドボンと直接加えて仕込んでいます。この米麹のやさしい甘みが加わることで、さらに塩分が低く、とてもまろやかな味わいに。加えて、末廣醤油の特徴でもある穏やかな香りも魅力のひとつ。見た目の色や味わいの濃さは違っても、「淡紫」と同じく、やさしい香りで魚の味を引き立ててくれます。そして何より、再仕込醤油ならではの濃厚なうま味が、赤身の生臭さをほどよく消し、魚のうま味をぐっと強く感じさせてくれるのです。
個人的には、赤身の刺身の中でも、特に旬の魚が手に入ったときには「濃紫」をおすすめします。脂がのっていて、口に入れた瞬間のとろけるような食感、それが、旬の赤身の刺身のいちばんの醍醐味です。その味わいを邪魔することなく、むしろ引き立てて、うま味を何倍にも感じさせてくれるのが「濃紫」のすごいところなのです。とろけるような赤身の刺身に、ぜひ一度あわせてみてください。「刺身って、こんなに味があるんだ」と、きっと驚かれると思います。

つれそい/南蔵商店(愛知県)
【赤身に合う醤油】の2本目は溜醤油です。
溜醤油は、淡口醤油・濃口醤油・再仕込醤油と、原材料の比率が大きく異なります。大豆の割合が多く、仕込み水は少なめ。さらに、長い時間をかけてじっくり熟成されるため、色も濃く、どろっと濃厚で、うま味は醤油の中でもトップクラスです。よく、「九州の甘くてとろっとした醤油=溜醤油」と思われがちですが、実はそれは別物。溜醤油の主な産地は中部地方で、塩分濃度は濃口醤油とほぼ同じ。決して甘い醤油ではありません。ただ、その濃厚なうま味を、味覚として「甘さ」と感じる方もいらっしゃいます。これは砂糖のような甘さとは違う、素材の奥にあるまろやかさのようなものかもしれません。
「つれそい」は、愛知県産の丸大豆を100%使用したグルテンフリーの醤油です。仕込みには、大豆に対して水を半量しか使わない「五分仕込み」という方法を採用。そのため、うま味がぎゅっと詰まった濃厚な仕上がりになっています。また、桶の底から滴り落ちる濃厚なエキス(生引き)と、諸味を圧搾したものをブレンド。ドロっと真っ黒な溜ではなく、赤褐色でキレが良く、フルーティーな香りが特徴です。再仕込醤油との大きな違いは、原材料の配合と塩分濃度です。「つれそい」は大豆100%仕込みのため、大豆のうま味がとても強く、塩分は程よく感じられます。
おすすめしたいのは、普段スーパーなどで手に入る赤身の刺身。食べた瞬間、魚よりも先に醤油のうま味がじんわり広がり、赤身の生臭さをしっかりと消してくれます。後味には、醤油の濃厚な余韻がふわっと残ります。とはいえ、「つれそい」は強すぎない。再仕込醤油よりは濃厚ですが、ドロッとしすぎず、赤身の刺身をおいしくしてくれるちょうどいい濃さなのです。

丸大豆生しょうゆ/森田醤油(島根県)
最後は【迷ったときに頼れる1本】の濃口醤油です。
いわゆる一般的な醤油と呼ばれる濃口醤油。大豆と小麦の割合は1:1で、うま味・甘み・香りのバランスが絶妙。何にでも使いやすい万能タイプです。でも、ここで一つ大事なことを。「濃口醤油なんて、どれも同じじゃない?」そう思う方もいらっしゃるかもしれません。ところが、職人醤油には濃口醤油だけで約40種類もあるんです。たとえば、木桶仕込みの濃口醤油。その木桶に住みついている微生物の種類は、蔵ごとにまったく異なります。その違いが、香りや味わいとしてはっきりと現れるんです。中には、「栓を開けただけで違いがわかる」ほど個性の強いものも。さらに、濃口醤油は最低でも1年の熟成。長いものでは3年熟成というものもあり、この熟成期間によっても風味は大きく変わります。
その中でも刺身におすすめの濃口醤油といえば、迷わずおすすめしたいのが「丸大豆生しょうゆ」です。リピーターさんはもちろん、新しく試してくださる方からも指名買いが多い森田醤油の一品。原材料は、国産の大豆と小麦、そして天日塩だけ。社長の森田さんが「自分の目で見て納得できる素材しか使わない」と語る通り、安心できるものだけを丁寧に仕込んでいます。そして、この生(なま)醤油は火入れをしていないのですが、精密なろ過で酵母を取り除いているので、開封前は常温保存が可能です。澄んだ色、すっきりとした味わい、クセがなく香りも穏やか。
どんな魚でも優しく包み込んでくれるので、「この魚には、どの醤油が合うかな?」と迷ったときには、ぜひ使ってみてください。海鮮丼のように、さまざまな種類の魚が一度に並ぶときにもぴったり。さらに、魚全般と相性が良いので、焼き魚にもひとまわしするだけで、魚の香ばしさがぐっと引き立ちますよ。
文:もーり(職人醤油)
オプションを選択