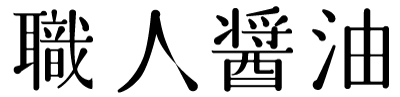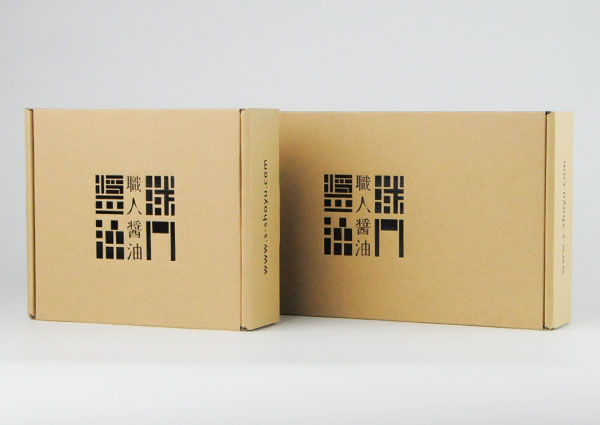記事: 木桶醤油
木桶醤油

伝統的な木桶仕込み醤油
木桶(きおけ)でじっくりと発酵・熟成させた醤油。それは、江戸時代までの日本にとってごく当たり前の光景でした。和食の基礎を形づくる醤油、味噌、酢、味醂、酒などの発酵調味料は、すべて木桶で仕込まれていたのです。
しかし高度経済成長と効率化の波の中で、木桶は「時代遅れ」とされ、醤油業界でもその姿は急速に失われていきました。現在、木桶で仕込まれる醤油は全体の1%以下。まさに絶滅寸前まで追い込まれました。
ところが2000年以降、風向きは変わります。若手の醸造家たちが「味わいの奥行き」「蔵ごとの個性」に改めて価値を見出し、木桶を使った仕込みを復活させ始めたのです。今では、木桶は再び「本物を求める蔵元が選ぶ容器」として注目されています。

100年以上つかえる木桶
木桶の寿命は長く、100年以上、時に150年にわたり使い続けられることもあります。しかし一時は、その強みさえも軽視されました。高度経済成長期には機械設備への転換が進み、木桶は次々と廃棄されていったのです。
醤油だけでなく、味噌や日本酒の業界でも同じ流れが起きました。新しく木桶を導入したいと考える蔵元は皆無となり、木桶をつくる職人への発注は途絶えました。その結果、2メートルを超える大型の木桶をつくれる職人は激減。2010年頃には全国にただ一組しか残らず、絶滅の危機に瀕しました。

小豆島からはじまる木桶復興の動き
ヤマロク醤油の声掛けから始まった「木桶職人復活プロジェクト」は、木桶と職人を未来に残すための全国的な取り組みです。毎年1月、小豆島には全国から蔵元や関係者が集まり、共同で木桶づくりが行われます。職人と蔵元が力を合わせて新桶を組み上げる。この活動をきっかけに、新たに木桶を導入する蔵元も現れ始めています。

木桶による発酵文化サミット
全国の木桶仕込み蔵が連携し、年に一度開催しているのが「木桶による発酵文化サミット」です。流通量がわずか1%にまで落ち込んだ木桶仕込み醤油を、まずは2%にまで増やす──そんな目標を掲げています。
そこにあるのは、同業者同士の健全な競争心。足を引っ張り合うのではなく、お互いに品質を高め合いながら、木桶仕込みの魅力を広めていく。かつて分断されがちだった醤油業界に、横のつながりと新しい風をもたらしています。

若い醸造家が集い始める
時代遅れと見なされていた木桶が、今では20代、30代の若手蔵人を引き寄せています。日本全体としては醤油の生産量もメーカー数も減少傾向にありますが、不思議なことに木桶仕込みの蔵には息子や娘が戻ってきているのです。
彼らは伝統をただ守るのではなく、木桶を「自分の個性を表現できる舞台」として捉えています。木桶でしか生まれない複雑な味わいは、消費者からも支持され始めています。時代の流れが変わり、木桶が再び「未来を担う選択肢」となろうとしているのです。

木桶醤油の魅力はクラフトビールのような多様な個性
醤油をつくる木桶は高さ2~3m、直径2~4mほどで、100年以上使うことができます。そして、木材の表面の微細な構造に微生物がすみつき、独特の生態系をつくりあげています。
これが木桶の最大の特徴で、百年を超える歴史の積み重ねや気候風土に応じてオリジナルな微生物の個性が、その蔵元にしか出せない風味や味わいを醸しています。

自然がつくる味
木桶は鉄釘や接着剤を使わずに自然の素材でつくられた容器です。発酵環境は、人工的な温度コントロールではなく、四季の温度変化による「天然醸造」。
寒い時期に仕込み作業が行われ、夏にはぷくぷくと発酵がはじまります。春夏秋冬によって、湿気が多ければ吸収し、寒い時には保温する。木桶はその表情を変えながら醤油に適した環境をつくります。

時間がつくる味
木桶の寿命は100年~150年といわれ、何世代に渡って使い続けられています。現役で活躍している桶の多くが明治~昭和の初期につくられたもので、その木桶を有する醤油蔵はさらに長い歴史を刻んでいます。
木桶の素材は杉であることが多く、その育成には数十年を要します。さらに、奈良県の吉野杉のような良質な材木の育成には、山づくりから行う必要があり、そう考えると数百年に渡る先人たちの積み重ねがあることが分かります。

人がつくる味
日々、異なる表情を見せる諸味。その年によって出来栄えも変わります。「いつも違うから、いつも心配…」「木桶を信じて任せています!」「手はかかるけど、その分、楽しい」と蔵人の接し方は様々。
繊細な蔵人は手をかける頻度が多くなり、大胆な蔵人は新たな製法に果敢にチャレンジをする。醤油の味わいは蔵人の性格に似てくると言われています。ただ、共通するのは自分たちがおいしいと感じる醤油をつくること。より個性を活かすために木桶が見直されています。

海外からも注目を集める木桶醤油
木桶醤油は今や日本国内にとどまらず、世界からも熱い視線を浴びています。輸出向けの大規模展示会「FOODEX JAPAN」では、毎年30社近い木桶醤油の蔵元が合同で出展。ブースには世界中のシェフやバイヤーが訪れ、実際に味わい、香りを確かめながら「KIOKE SHOYU」の魅力に触れています。

若手の蔵元たちがつくりだす醤油の世界
木桶というキーワードを軸に、若手の蔵元たちが世代を超えて連携しはじめています。20代、30代の蔵人たちが集まり、お互いに技を学び、情報を共有し、ときに一緒に桶を組み上げる。そこには、かつての競争の枠を越えた「仲間意識」と「未来を築く使命感」が生まれています。
彼らが目指しているのは、単なる伝統の継承ではありません。木桶を通じて、それぞれの蔵の個性を最大限に引き出し、世界に向けて「多彩な醤油の表現」を届けることです。フランス料理のシェフがソースに木桶醤油を使い、アメリカではBBQに、台湾では家庭料理に──。使い方も広がり、醤油の世界は新たなステージへと進みつつあります。